投稿日: 2009年11月29日
「ヨーロッパの食とギフトを学ぶ研修旅行」(9)
「グルメ班」報告記
今読むと恥ずかしい記述であるがその要約を掲載したい。
英国では “You are what you eat.” といって「君が何を食べているかをみれば、君がどん
な人かわかる」といわれている。私はこの言葉に加えて、「どんな食べ方しているかをみ
れば、君の実体がさらにわかる」といいたい。
今回の研修旅行では、年齢差が唯一の差で、あとは菓子を中心とする食品業者が、今回の
旅行の狙いである「ヨーロッパの食生活とギフト習慣を学び、今後の商品企画を探ろう」
とする人たちのグループ旅行であった。この熱心なグループが国をかえ、場所をかえ、品
をかえてコンヴィーブした2週間であった。30余回のコンヴィーブを通じ、オビさんご
夫婦招待のホームパーティーが最も印象に残った。ご夫妻のてづくり料理に快哉を叫び、
第一位の賞を差しあげたい。これが「グルメ班」の総括である。
20名のグループを家庭に招くということは、とても生半可な気持ちでは引受けられない。
オビ夫人の特製ハーブ茶の数杯が、食後酒の効用をはるかに超えるものと吃驚したのは、
私一人ではあるまい。あの大きなテーブルにところ狭しと並べてあった料理のすべてと、
ホスト、オビさん焼くところのソーセージ4本をたいらげ、デザートを全種類征服し、な
お胃にもたれなかったといえば、どんな食事であったかがおわかりいただけるであろうか。
食べる人の気持ちをはかり、消化のよいものをつくる主婦の手料理で招待された私たちは
幸せであった。こころとこころの触れあう食事こそが健全な食事のあり方で、グルメの目
指さねばならないところであろう。オビさんにこのパーティーを依頼したアウェハント・
静子さんによると、ご夫妻は私たちのために一週間前から準備されたと聞く。私たちの食
欲が最も湧いてきたとき、おもむろに薪に火をつけ、ソーセージを焙り、私たちに供した。
薪のスモークを嗅ぎわけながら食べるソーセージが、こんなにもうまいものであったこと
をそれまで知らなかった。
何がオビ一家をしてこのように異国人のために気配りをさせるのであろう。オビさんは私
たちとの2時間余りの時間をどんなメニューで、どのように過ごせば最も喜んでもらえ、
しかも自分たちもこころの満足が得られるかを一週間にわたって考えられたという薪を
集め、割り、それに火をつけ、ころ合いをはかってソーセージを焙り、供する。
あのパーティーのメインディッシュはソーセージであり、それはホストであるオビさんが
自らの手で焼いて私たちにサービスされる。これはホームパーティーの作法にかなったも
のであった。何よりもあの慈愛に満ちた眼差しで差しだされるオビさんの手さばきをみて、
一瞬私は茶道の袱紗さばきを連想した。正に洋の東西をとわず、茶のこころ、一期一会の
もてなしのこころをみたのである。
オビさんの長男が自分の制作したインテリアの木工品を分解して見せ、再び組みあげてい
くときの瞑想的な眼差しの中に父親譲りの生きざままでをみた。彼の持つ東洋的な憧れを
木工の作品にうちこむ姿に日本人である私がたじろいでしまった。私たちは余りにも物質
的な価値観に毒されすぎているのではないだろうか。
私はパーティーの雰囲気を盛りあげようと、お嬢さんの伴奏でシューベルトの「楽に寄す」
を、そしてオビ夫人の伴奏でヴェルディの「プロヴァンスの海と空」を歌った。20時間
をこす旅の疲れで私の声は悲惨であった。しかし彼女たちが初見で伴奏してくれた腕前に
恐れ入った。オビさんは小学校の定年前の校長先生であるところから、夫人はきっと音楽
の先生であったのではないか。
雰囲気が盛りあがったところで当日が誕生日である秋坂さんとアウェハント・静子さんの
誕生日を祝して “Happy birthday to you!” の大合唱でパーティーは最高潮に達した。当
日ホストを手伝っていた近所の美容師である若いクリスティーヌから私たちのグループか
ら選ばれた中村逸平さんにキスがおくられた。逸平さんは突然のキスに照れた。しかし満
面の笑顔だった。オビ夫人が額に汗をにじませながら一人、一人と手を握り、別れを告げ
るかたわらに、オビさんがそれを眺めつつ満足そうに頷いていた。
イタリアでの6日間の旅。
小嶋さんの振舞いについて。
振舞いがもてなし、馳走につながること。
グルメはグルメを知る。心から楽しそうに食事をする彼の姿は、見ているものを楽しくさ
せる。魅力というべきか、魔力というべきか。一種独特の風格がある。自分の得意なレパ
ートリーをもって世界各地のオペラハウスを飛び歩いている歌手として、彼はオペラ歌手
仲間、オーケストラ仲間と常に食事をとっている。音楽をする人たちは概して食にうるさ
い。私たち一行が食品関係の業者であれば、一人一人が食についてうるさい集団であるこ
とを彼は見抜いていた。食事が期待通りでないときや、配膳に手間取るようなことがある
と、小嶋さんは涙ぐましいほどの奮闘ぶりで私たちを笑わせたものだ。酒の話、女の話、
珍味の話など。
イタリアの風物と、イタリア人を愛している彼の解説には並々ならぬ彼の知的考察が含ま
れていた。彼は少々、下世話なメタファーに包んで、聞くものを笑わせながら話すので、
彼の博識を往々にして聞き逃してしまうことが多かった。彼のグルメぶりはミラノからラ
ンギーノまで100余キロを車でぶっ飛ばして、生ハムを食べに行くという。美味探求こ
そが美味礼賛につながると私は思いこんでいたが、彼の食べかたをみていると、美味礼賛
が先であると気づいた。
たしかに美味しいと心から思わなくては美味しものも美味しいとは言い難い。ブルーチー
ズのような臭いの強いものは美味礼賛に自ら縛られていくようなところがある。グルメを
語るときに私は「たべもの」そのものよりも、食事をともにする人の気持ちを大切にする
ことが大切だと思う。これについては先にも書いた。私は小嶋さんの人柄は食事をすると
きの姿にそのすべてが出ているように思う。周りの人たちにエーテルのような作用で「よ
ろこび」を感じさせるよう配慮し、振舞うことである。これがグルメにとって欠かすこと
のできない資質であろう。
当初、私たちのこの研修旅行の計画を実施するために、ウンブリア州の役所との折衝、受
け入れの準備に奔走したのは小嶋さんの奥さんであった(モロゾフのミラノ駐在員)。前
年の暮れに突然、不慮の交通事故で亡くなられ、この計画は頓挫したかに思えた。小嶋さ
んが、奥さんの意志を継いで計画を実行することが亡き奥さんへのよき回向だと思ったそ
うで、この旅行企画は軌道に乗った。この話を松宮さんから聞いて涙せずにはいられなか
った。小嶋さんが悲しみの中にあって、私たちに示された優しく、こまやかな心くばりと、
気づかいのすべてを尊敬する。悲しみの中に力ありの言葉を噛みしめた。
[小嶋健二はその後再婚したが、数年後に癌で亡くなった。1945年~1993年]
「グルメ班」記は、この後、先週アップした「ル・プレ・カタラン」について書いたが、
やはり詳細な評論は避けた。すでに「ル・プレ・カタラン」は代が替わっているようであ
る。すべてのものは無常である。食事もお茶とおなじく一期一会である。本当の伝統的な
フランス料理はもうパリに存在しない。田舎を自分の足で巡り歩いて見つけるしかない。
近年は、ベルギーにフランス料理らしいフランス料理があるといわれる。パリの昔のよき
時代のお菓子もパリにはない。ところがそれが東京にある。河田勝彦のつくるフランス菓子
である。パリから東京へ見学にくる。
<この項おわり>

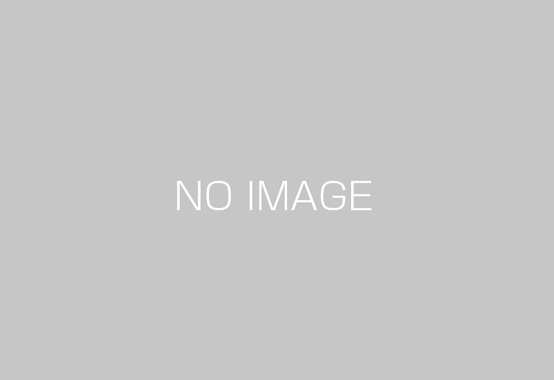



この記事へのコメントはありません。