投稿日: 2010年8月29日
英国のスイーティー、ベルギー視察 (2)
1989年4月11日、日帰りでバーミンガムにあるキャドバリー(Cadbury)の本社工場を須田バイヤーと見学に行った。私がイギリスとベルギーに行くことを知った中野義巳が社長の江崎勝久にこのことを知らせた。それで日本を出るまえに社長から呼び出しがあり江崎グリコ本社でキャドバリーの日本総代理店、株式会社フランシスの社長、ジュリアン・エフ・バートと引きあわされた。彼は典型的な英国商人であった。キャドバリーの製品が江崎グリコのチャンネルで自分が期待しているほど売れていないので何か良い智慧はないか考えてくれということであった。
バーミンガムまで1時間半の汽車旅であった。工場に着くと Cadbury International Limited のマーティン・ドレーン(Martin E. Drane)が愛想よく迎えてくれた。事前にダイエーのバイヤーを同行すると伝えていたため精一杯の歓迎をしてくれた。工場はやけに広く大きかった。仕込み室から成型ライン、包装ライン、出荷仕上げラインまでの距離は巨大な工場を取り囲むようにラインが走っている。その長さは2キロメートルもある。ラインの長さが長ければ長いほど製造スピードは速くなり一日あたりの生産量は大きくなる。
この馬鹿でかい工場で1カ所不明なところがある。それはミルクチョコレートを仕込むところである。通常、ミルクチョコレートの仕込みはミキサーに砂糖、カカオマス、ココアバター、粉乳、レシチンを入れて攪拌する。ところがキャドバリーは大きく違うのである。ここはクーベルチュールに液乳をいれて攪拌(コンチング)するのだ。そして液乳の水分を飛ばすのである。ミキサーともコンチェとも違う巨大な機械は遠くからしか見せてくれなかったが、この工場の心臓部分だ。温度はどれ位かけるのかとドレーンに聞いたが答えてくれなかった。この行程はどれ位時間がかかるのかと質問しても回答はなかった。これが伝統のミルクチョコレートの作り方であり秘密にしているところだと言う。味はカゼイン臭がつよくチーズのような風味がある。ハーシーのミルクチョコレートも同じような製造法である。日本人には味は重くスイスミルクチョコレートとの味とは比べるべくもない。
工場見学中にふとしたことから須田正人はラガーだということをドレーンが知った。途端に彼の態度ががらりと変わり会話は冗長になった。一晩バーミンガムへ泊まっていけとしつっこい。その訳は工場見学の途中のティーブレイクのときに判明した。ドレーンは英国のラグビーナショナルチームの一員であった。昼食は特別なところへつれていくといって”Classic Car Museum Restaurant” に招待してくれた。数々のヴィンテージカーに囲まれて食事をすることも悪くはない。ドレーンが beautiful という料理の味はやはりイギリスの料理であった。味は今ひとつであった。
彼は今度日本を訪問したらぜひダイエーを訪問したいとはしゃいだ。どのようなプレゼンを持って行くつもりかと尋ねた。英国で期末セールのときの価格と同じにして、同じ景品をつけると言う。景品は何かと聞くと商品価格の100倍を現金で払うのだという。「ドレーンさん、日本の景品法では、10倍までと決められているので100倍はだめですよ」と須田正人は言った。100倍の景品をつけるとどれだけ在庫が残っていても一掃できるとドレーンは言った。英国のチョコレート屋は楽だ。壽屋の「トリスをのんでハワイへ行こう」とか不二家のミルキーの景品問題など日本での事情を説明した。(1962年に法律成立)ドレーンは大きな落胆を示した。
須田バイヤーとのロンドンでの約束の日程が終わると女房が急に不足を言い出した。ダイエーが手配してくれたマーブルアーチの近くにあるカンバーランドホテル (Cumberland Hotel) は4星の典型的なビジネスホテルであった。しかし日本と比べると薄汚れたベッドやトイレが不潔でたまらないという。日本から持ってきたアルコールに浸した消毒綿花も使い果たしそうだと騒ぐ。ソニーの盛田昭夫の常宿、インオンザパーク(Inn on the Park)に電話したがあきはないという。思い切ってリッツ(Ritz)に電話をかけたところ、幸い部屋があるという。早速宿替えをした。
金を出せばこんなに素晴らしいホテルがあるのかと女房は目を丸くする。ロンドンでどこのホテルが良いかという情報を事前に知っているかどうかの問題である。インオンザパークのお昼のビュッフェはホテルオークラから本格的な鮨の職人が来ているから良いとか、細かな情報がある雑誌の「ロンドン特集」に書いてあった。ロンドンで鮨など食べたくないと夫婦揃って頷きあった。リッツのレセプションや電話のオペレータが使う英語はまさしく上品なキングスイングリッシュであった。まえのホテルでコックニー(Cockney)に悩まされていたので清々しい気持であった。
“On The Town” という小冊子を見ていた女房がモーツアルトのオペラ、「皇帝ティトの慈悲」(La clemenza di Tito)を観たいと言いだした。チケットをリッツで取ってもらおうと思いオペレータに電話をかけた。今日の今日のチケットはどこでもおいそれと買えない。電話をかけるとすでに sold out だという。プレミアムをつけてもいいと言ったが通じない。じゃあ、もういい、というとオペレータは通じるまで話せという。通じていたのだ。どれくらいプレミアムを払うのかと聞かれた意味が通じなかったのは自分のほうであった。倍でもいい、と答えると、”You did it! Thank you, sir. Good afternoon. Sayonara.” と。
リッツのアフタヌーンティーは給仕のオーダーをとる仕草や言葉遣いが、日本のおもてなしのこころ以上のものを身につけていた。これが階級社会のつくりだした真の職人芸だと思った。ことばの最後につける ”sir” や ”madam” はとても一朝一夕には身につかない。供されたサンドイッチ、スコーン、ケーキも私の職業上の見地からみても不味くはなかった。調度品のすばらしいこと、窓にかけられた緞帳やレースのカーテンの豪華さ、テーブルまわりの調和のとれたテーブルウエアがいやが上にもダイニングルームの雰囲気を高める。天井にレリーフが施されている。豊かな気持になって嬉しくなった。
部屋にもどると電話に赤いランプが点滅している。かけるとオペラのチケットがコンシェルジェに届いているという。プレミアムは20パーセントであった。早速コンシェルジェのところへ行った。ロンドンに来たのであればミュージカルを楽しみなさいよ。今夜のチケットでもプレミアムなしでとれますよ、と親切に言ってくれる。ありがとう、ところでコヴェントガーデンにはどう行けばいいかと尋ね、メモをもらう。
映画『マイ・フェア・レディー』で、オードリー・ヘップバーン扮する花売り娘のイライザがヒギンズ教授と出会ったシーンを思いだしてください。ここはロンドンの下町なのです。コックニーを喋らないと肩身が狭いのです。リッツからコヴェントガーデンマーケットに来れば自然に『マイ・フェア・レディー』が想起される。
オペラが始まる前に行きたいところがあった。それは「クラブトリー&イーヴリン」(Crabtree & Evelyn)であった。マレーシアナンバーワンのパームオイルの産出会社がアメリカベースでボディーソープを中心にスキンケェア商品と雑貨のマスマーチャンダイズチェーンストアを世界的に展開しているブティックである。ここに近年の流行商品であるベルギーチョコレートのプライベートブランドが発売されていたことを知ったからである。ベルギーチョコレートのプライベートブランドは店頭にならべられていた。ソニークリエイティブプロダクツと江崎グリコを結びつける見本がほしかったというのが本音である。ノイハウス&モンドースの工場で作っているのではないかと思われた。ごくありふれたバーチョコであった。ソニークリエイティブプロダクツにしろ江崎グリコにしろマスプロ商品でなければ採算にあわない。モンドースの工場はマスプロ商品しか製造していなかったが、発注者の「クラブトリー&イーヴリン」としてはブランドが売れているノイハウス&モンドースに魅力を感じるのだろう。ブランド志向は日本にかぎらずマスマーケティングには必要な要素なのであろう。
<つづく>

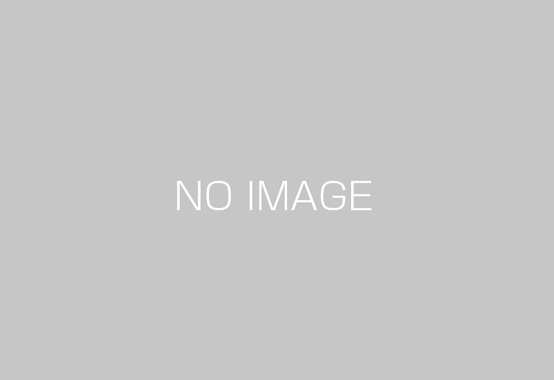



この記事へのコメントはありません。