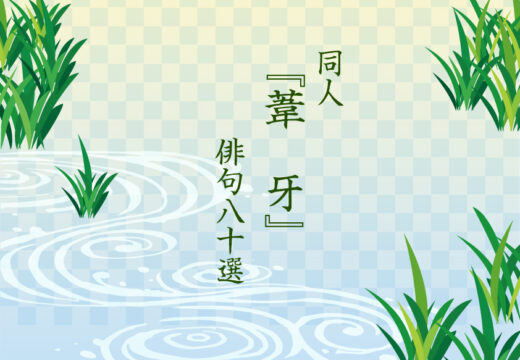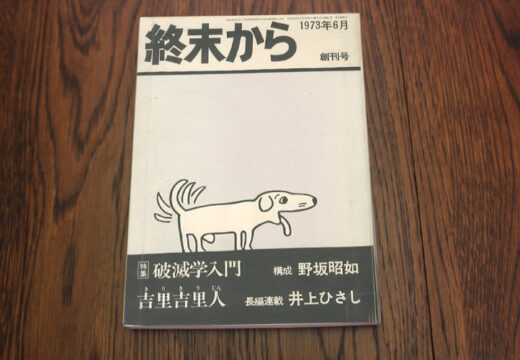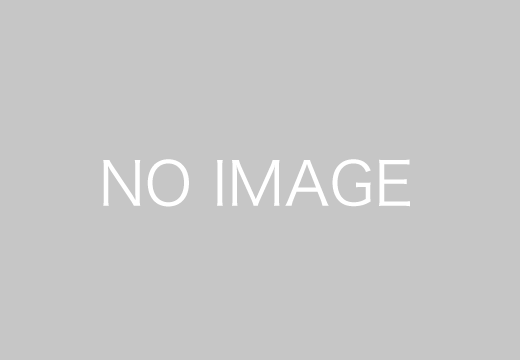【一】
「くそっ」、「ちっ」といいながらくらしている。
朝起きると、まず布団の端に腰を据え膝を立てる。障子の仕切りの柱をつかみ、足腰に力を入れて腕で引っぱりながら「えい、やっ」とからだをもち上げ立ち上がる。
その時「くそっ」と声が出る。
足腰が自然に働かなくなっている。こうなって三年ほどは経っているだろう。何がきっかけということではなく、気がついたらこうなっていた。
手足なんていうものは、こうしようとすればこう動き、ああしようと思うまでもなくああ働くものだろう。
予想外の老年にまだ慣れられない。
「記憶の中の自分」と「現実の自分」の乖離の狭間でくらしているのである。
【二】
野菜の煮物を作ることがある。材料は人参や玉葱、里芋、大根、蓮根など。豆腐や鶏肉を加えることもある。
出汁には「焼きあごだし」の顆粒を使う。これに昆布を細かく切って入れる。水はたっぷり。料理酒とみりんも気分量。塩、醤油は使わない。塩分はあごだしや料理酒から出る。
水分を多くするのはスープとしても食べるから。
野菜はできるだけ同じ大きさに切り、とろ火でコトコト煮る。野菜の甘味が出てくるような気がする。
包丁のように手先を使う仕事は、ぼけ防止にもなるらしい。二、三日ひとと口をきかない日が続くことがあると、だんだん言葉をわすれてゆくようである。煮物づくりは喫緊の大事なのだ。
【三】
九十五歳八か月という女性と知り合った。週一回半日コースというリハビリに通っている。女性はこのコースの二十人ばかりのメンバーの一人。
和服を仕立て直した花柄のブラウスを着ておられた。それがとても粋で洒落ていた。背中が少々曲がって、補助車を押して歩いておられたが。
長靴型の自動マッサージ器を並んではいて雑談を楽しんだ。会話が滞ることはなかった。
リハビリに通うひとの多くは病後の体力回復のために通っている。しかし加齢による衰えを止め、体力維持のために通ってくるひともいらっしゃる。老女はその一人。
年の暮れ、来年またお会いしましょうと別れたが、帯を裁ち直した素敵なパンツをはいておられた。
【四】
買い物は週一回、ヘルパーさんに頼んで近くのコープ店で野菜や食品などその週に必要なものを買ってきてもらっている。コープの宅配便も利用しているが、一品当たりの分量が多すぎて欲しいと思っても注文できないことが多い。「ふん、一人暮らしはどうせたいした売り上げにはならねえからな」とひがんでいる。
マンション(と呼ばれている共同住宅)を降りてゆけば、細い道一本へだててコンビニ店がある。このコンビニがいつの頃からか品数を増やしてきて、最近は週末の一日、地元の野菜や果物を置きはじめた。重宝していたら巨きな組織に吸収されたらしい。
どんな店があらわれるのかわからないが、売りたいものしか売らない店では困る。小店の集まった商店街が四十年ほど前には繁盛していたと聞いているのだが。
【五】
ことばが出ない時がある。単語が出てこない。ことに名詞、固有名詞が抜け落ちてしまっている。
先日は長女と電話でやりとりしていて、「ヨーグルト」が出てこなかった。「腸内フローラ」などと周辺のことばはちゃんと出てくる。会話はようやく、
「それ、ヨーグルトじゃないの」
「うん、それ。ヨーグルトとバナナをパンケーキにそえて朝食にした」と成立する。
会話の最中に、そのことばを口にしようとする寸前にふっと脳から消えてしまうのだ。記憶装置にゆるみが出ているらしい。人の名前、昨日読んだ本のタイトル、などなど。
これは認知症の初期症状かもな、と思いながら、出来るだけ早く忘れたことばを呼び戻そうとしている。
【六】
木曜日になると、ホッとする。
今日から三日間、夜食に何を食べようか、あれこれ考えなくてすむ。
木曜日から金、土と三日間夜食の弁当を取り始めて二年余りになる。これを始めてから今夜は何にしようか、鶏肉か魚か、野菜は何があったろうと冷蔵庫を点検しなくてもすむようになった。
弁当は届けてもらえる。市内のお母さん達のグループの手作り。主菜の他に小鉢風に三品副菜がついている。優しい味の家庭料理でコンビニや駅ビルなどに出店している料理店等で買う味の濃い弁当とは違ってあきることはない。
弁当を受け取るときにお母さんたちとちょっとおしゃべりをする。それで今日もひとと会えたという気にもなれるのである。
【七】
朝はパン食である。共稼ぎの結婚だったので、支度が簡便な方になった。それが五十余年続いた。
食パンが主だがバケット、バタール、ロール、クロワッサンなど。近くに若い夫婦二人で営んでいるパン屋さんがあり、カンパーニュが美味しいのだが焼く日とこちらの買い物日がずれていてめったに入手できない。
副菜は定番のハム、ソーセージ、ベーコン、卵、チーズ。それに野菜炒め、焼き野菜、野菜スープ、ポタージュなど。
焼き野菜はフライパンに七~八ミリ厚さに切った人参、ジャガ、エリンギ、半月切りの玉葱などを並べ千切ったキャベツをかぶせ蓋をして弱火で焼く。十~十二、三分くらい。
中華鍋でキャベツを蒸し煮する方法が伊丹十三のエッセイにあり簡単でうまい。
【八】
独居暮らしが続くとひとと会話を交わすことの大切さを身に沁みて感じてくる。
意図しなければひとと会わない、話もしないという日が週二日ある。
しかし毎晩九時四十分を過ぎると娘から電話がかかってくる。「もしもし、どーもどーも、今日はいかがでしたか」
そこでその日一日の出来事をしゃべる。洗濯をした、定期検診に行ってきた、誰それから電話があった、などなど。
娘は双子の男子五年生の母親で、学校行事への手伝い参加、担任教師との話し合い、PTAの役員当番など多忙を極めるが、この夜の電話は欠かしたことがない。
お陰で娘一家の一日、子供たちのくらしぶり、世間のさまざまを知ることができ、その夜の安眠も得られている。
【九】
からだじゅうが痛い。首から肩、背骨に腰骨、大腿骨に膝、足首。むろん筋肉も筋も痛む。
だから日常は痛みを無視して動いている。そんなものは無い、ということにして生きる。
友人、知人から電話がかかってくると、話はすぐ「体調はどう」となる。「首も肩もガチガチ、腰も膝も夕方には立っているのが苦痛になる。夜は仰向けに寝る迄が大変だよ」
「ふむ、私も同じ。この齢になりゃあ皆あたりまえ、あはは…」
話はやがて「誰それが心臓を悪くして入院しているらしい」などと、情報の交換だ。
何年かぶりかで最後のクラス会をやろうという誘いがあった。はて、出ていけるかなと考えていたら、「中止になった」という電話が入った。
【十】
友人と本を交換して読んでいる。文庫本が主で新書が混じる。
郵便局からスマートレターという特定封筒を使うと1kgまで180円で郵送できる。普通小包を利用する手もあるが手続きが少々めんどうくさい。
友人が送ってくれるのは自分ではほとんど手を出さないものが多い。しかし読んでみると、なるほどと感心させられる。
友人は高校時代のクラスメートで、大学在学中も交際は絶えなかった。卒業後、同じ業界に就職したことも手伝って、以後八十歳を過ぎる現在まで続いた。
この年令になって、こういう友人を持てていることはありがたい。
郵便受けに本の小包が入っているとこの上なく幸せである。
【十一】
昭和二十年八月十五日、私は38度線の北約20キロ、開城(ケソン)市郊外の小学校にいた。満州新京から一家五人(父親は吉林の工場に単身赴任)で疎開していた。
正午、玉音放送があるというので校庭に集合、雑音ばかり耳に入る中で時々人の声のまじる放送を聞いた。内容は理解できなかったが大人たちの反応で、戦争が終わったことを知った。喉が渇くので水道のある用務員室に行った。
台所には小母さんとその娘がいて、娘は蠅取紙の飴色の薬を指でこそいでは舐めていた。いやがるふうでもなく、顔をしかめるでもなく、ご飯を口に運ぶように淡々と舐める。びっくりしている私に「虫下し」だと小母さんが言ったと思う。
敗戦の日というと、この事を思い出す。
【十二】
敗戦の年の冬、十一月か十二月のある日の夕方、三角窓から下の道を眺めていた。
雨が蕭条と降っていた。
道の向かい側は空き地で土管などが置いてあり、子供たちの遊び場になっていた。
ぼんやり眺めていると突然、鉄色の道路の右端に白い物が二つ現われた。
白い物は大小で、まあたい袋(麻亜袋)と呼んでいたものに違いなかった。
大きい白い袋が母親で、小さい袋が娘であったろう。足に靴はなく布を巻きつけてあった。大小の袋はやがて道路の左に姿を消した。
どういうわけでか開城から無蓋車に乗せられて戻った新京の社宅には、ソ満国境から逃げてきた満鉄の機関士、機関助手二十三人が住みついていた。
白い袋の母娘を迎い入れる余裕は無かった。
【十三】
その女性(ひと)と女の子を見たのは引き揚げの無蓋の貨物列車の中だった。
背が高く、男のような躰つき角ばった顔つきの女性で灰色の男物のズボンをはいていた。その背中に、斜めにザン切り頭の女の子を結わいつけていた。
様子を眺めていた母が小声で何か注意をした。もっとちゃんと面倒を見てやれ、とでも言ったらしい。女性は母をまったく無視していた。
茫々と地平線に広がる高粱畠を大きな夕日が覆っていた。
車中のあちらこちらで食事が始まった。米を入手できなかったわが家は乾パンが代用だった。ふと気がつくと、女の子は大きな握り飯を持っていた。その握り飯から一粒ずつはぎ取っては口に運んでいた。一粒ずつ。
【十四】
引揚列車の終点は葫蘆島だった。遼東湾西岸の港。
在満日本人の引揚げは二十一年五月十四日に始まった、という(『日本植民地史2⃣満州』毎日新聞社)。私たち一家が南新京駅から無蓋車に乗ったのは九月二十一日。
収容所に入ったはずだが一週間いたのか、十日いたのか記憶は全く消えている。
引揚船は米軍の上陸用舟艇。甲板の下はだだっぴろい空間で、船尾の奥まで大勢の人がすわり込んでいた。渤海から黄海、東シナ海へと出た船は嵐に遭遇、嘔吐する人が増え、臭気が強くなった。
大麦に大根の葉っぱ、正体不明の何かが混じった粥が小さなコップほどの器に一杯配給された。下の兄につれられ炊事場にそのお焦げをもらいに行った。
【十五】
引揚船が佐世保湾に入った時に目に映ったもの、その印象を忘れることはできない。「これは何だろう」と思った。
緑色に赤や黄のまじった半円形の山々、緑色を帯びた海、青く澄明な空。大人になって知った箱庭の印象だった。
広島駅で動き出した列車からあわてて跳び降りた。父親が見まちがえた、夜の広島の街がホームから遠くの暗闇まで見渡せた。所どころに灯が見えた。
構内に止まっていた客車で眠り、翌朝芸備線に移り父親の故郷に向かった。
車中向かい側にすわった老婆から妹がお握りを一個いただいた。真っ白な大きなお握りだった。
たどり着いた伯父の家の前の田んぼの隅で、柿の木に一つ紅い実が残っていた。
【十六】
久しぶりに朝食用の野菜サラダを作った。
材料はレタス、キャベツ、玉葱、人参、スプラウト。
① レタス 小さく切る
② キャベツ 1mm幅に千切りする。
③ 玉葱 中玉半コ。できるだけ薄く切る。
縦半分に切り1mmよりもっと薄く切る。
④ 人参 「ツマ切り」の器具を使って3ぶんの1本ほどをけずる。
⑤ スプラウト 1パックをほぐして①~④を混ぜ合わせながら散らしていく。
一食分がガラス中鉢一つ。一回で二日分作る。味つけはエクストラ・ヴァージン・オリーヴオイルとアマニ油を適量ふりかけ食卓塩をパラパラとやるだけ。既製品のドレッシングもいろいろ試してみたが、我流がいちばんあっさりしていて満足している。
【十七】
今年(2020年)の梅雨は長かった。東京地方では七月の間、雨の降らなかったのはたった一日だけだったと、TVのお天気番組が解説していた。
処々で街が局地豪雨のために水浸しになり河川の氾濫で田畑や家屋が冠水した。
天候の異変は日本やアジアの東南地域だけではなく、東欧やヨーロッパも全域で同じような被害にみまわれたようだ。
私は旧満州の鞍山で生まれ新京(長春)で育ったのだが、梅雨の時期をおくったという記憶が全くない。
九月末には始まる冬の時期は長く、五月中旬まで続く。突然日差しが暖かく明るくなり草樹がいっせいに花をつけ花を散らす。それが一週間か十日もすると、焼けるような強い日射しの夏が一足跳びにやってくるのだ。
【十八】
「一日何をして過ごしている」のかと問われれば、「ぼーっとテレビを見ているか、本を読んでいるか」と答えるしかない。
現住地に引っ越してくるとき、持っていた書籍の半分ほどを売り、家内が亡くなった四年前の十月頃残りの半分も神田の古書店に引き取ってもらった。それぞれ二屯トラックに一杯分ほどだった。
いま読んでいるのは文庫本である。大半は駅近くのブックオフで100円~200円で買ったもの、あとは売れずに残っていた累年のもの。この中には現存しない出版社の文庫やとっくに絶版になり再版されていない文庫本もある。
お互いに手持ちの文庫本を郵便で交換して楽しんでいた高校以来の旧友は、残念ながら一昨年、三日救命室にいて亡くなってしまった。
【十九】
旧満州(中国東北部)は大豆が良く育つ土地だった。
国民学校四、五年生の頃、八月の終わりから九月の初めの頃、学校から新京市郊外の収穫の終わった後の大豆畑に、落穂拾いならぬ“こぼれ大豆拾い”に行かされた。
畑は広大でどこまでが畑なのか見当もつかないほどだったが、畝やみぞに機械で苅り取るときに殻がはじけてこぼれ落ちた豆がそこそこに見える。それを一粒ずつ拾って学帽に入れてゆく。最初は面白くて夢中になるが、すぐにあきてしまう。なにしろあっちにもこっちにも落ちているし、目のとどくかぎり畑は広がっているのだから作業は果てしもない。
それを見越してか、拾った量のコンクールがあり、一番になり講堂に立ったことがある。一つ上の兄が自分の分を足してくれたから。
【二十】
色に「彩度」と「明度」という色の「物差し」がある、と教えられたのは国民学校の五年生の時である。
なぜそんなことを教えられたのかというと飛んで来る飛行機の型と色を見分け、味方の飛行機か敵のものかを判別して先生に教えるためである。
太平洋戦争の末期、小学五年生ともなれば国防組織の重要な構成員とされた。国境を越えて、いつ米軍機が空襲をしてくるかわからない。昭和19年7月29日、鞍山・奉天(現審陽)大連が米軍機のB29に爆撃されていた。
敗戦の年の8月9日、新京も米軍機に空爆される危機というので満鉄社宅住人に疎開命令が出た。出発駅の南新京駅のプラットフォームに何故だか、大量の缶詰が放置されていたが、拾う人は一人もいなかった。
【二十一】
国民学校五年生のとき、選ばれてモールス信号(符号)を学ばされた。無線通信用の言語だと言えるだろう。欧文にも和文にもそれぞれの符号がある。
例えば、欧文のABCだと、
Aは・―、Bはー・・・、Cはー・―・
和文のイロハなら
イは・―、ロは・―・―、ハはー・・・
生徒は教官の後について、「トン・ツー」「トン・ツー・トン・ツー」「ツー・トン・トン・トン」と暗唱して覚える。教えられていた時は、短い文章なら符号に変えて口唱できていたけれど、敗戦後にはあっという間もなく忘れてしまった。
通信手段が高度に発達を遂げてしまった今でも、モールス信号を使っているところがあるだろうか。
【二十二】
新型コロナの感染者が急増するにつれて、卋界中の国の都市でロックダウンが行われてきた。それで思い出したことがある。
満州新京に住んでいた国民学校三年か四年の頃、社宅と大通り一本をはさんだ“満人居住地”で起きたことである。
満州は清朝時代以降、ベストの流行地であり、それを抑制するために時には悲情な手段が採られた。
社宅の隣の満人居住地区で採られたのもその例で、ある日、居住区住人を着の身着のまま追い出し、居住区の周囲を高いトタンの塀で囲み、菌の媒介者であるネズミが逃げださないようにして火をつけたのである。
居住区は三晩か四晩燃え続けた。
茶灰色の煙が街中をおおって、空は夕暮れ時のように昼日中も薄暗かった。
【二十三】
花の名前がわからない。
わかるのはコスモス、ヒマワリ、アジサイ、タンポポぐらい。
コスモスは満鉄の社宅の庭に咲いていた。それとロシアグサ。ロシアグサはキュウリと一緒に漬けて「ロシア漬け」を作る。さっぱりした味と香りの漬け物ができる。
アジサイは嫌いだから知っている。花の形が嫌いだし色も嫌いだ。花の色が変わってゆくのがいやだ。青紫の色がうっとうしい。幽霊花とよんでいる。
当地に来る前に住んでいた逗子の家の庭には、前の住人が植えた大きな株が一株あった。亡妻は喜んでいたが、何年か後、私が切り倒してしまった。花好きだった亡妻にはすまないことをしたと、思っているのだがアジサイ好きにはなれないままだ。
【二十四】
味覚が“子供還り”しはじめているらしい。
子供の頃、食べ物の好き嫌いが激しかった。というより、食べられないものが多かった、というほうが正しい。
「うどん」が食べられなかった。ぬるり、と細長い虫に見える。
喉を通り抜ける感触が耐えられない。気持ちが悪い。
豚の脂身が食べられない。胃の中で這い廻るような気がする。にゅるにゅる、べたべたと。
敗戦がその習性を変えてくれた。何であろうと、口に入れられるものは食べなくては生きていられない。虫だろうと“にゅるにゅる”だろうと。
それが現在(いま)、口に入れる物を選ぶようになってきた。
【二十五】
今年(2019)は四月から後、六、七月と異常気候が続いている。
気圧の乱高下に躰がついていけない。昨日と今日との気圧の極端な変化に対応できないでいる。
躰の気だるい日が続いている。
若く元気そうに働いているリハビリ施設の療法士の女性にきいてみたら、やはり、「気だるいです」ということだった。
ともかく、昼食後の一時間半は横になることにした。横になって文庫本に目を通す。眠くなったら枕元の電気を消して目をつむる。眠り込む日もあれば、ただ目をつむっているだけの日もある。それで一日をやりすごす。
曇天と雨天つづきである。
今夏は太陽に出会える日が極端に少なかった。体調不良はこれも大きな要因だろう。
【二十六】
六年生でも学校が終わったからといって遊んでいるわけにはいかなかった。
学校から帰ると大急ぎで、沖の田圃に向かう。
田圃の仕事は次兄と私、二人の仕事だった。腰をかがめて、分茎し生長する苗の回りに生え始めた雑草を掌で掻き取る。泥田の中をはい回って取る。
一番草、二番草、三番草と十日から二週間くらいの間隔を置いて田に入る。稲の葉裏には小さな棘がびっしり生えて、葉自体が刃のように鋭い。その葉が目に入ると傷ついて大変なことになるよ、と言われていた。
「満州の家の田はすぐわかる」と近所の評判だった。小さな手足の跡が泥田に残っていたから。「やれやれ、いたわしいのう」と小母さんたちの噂だった。
【二十七】
引揚げ一家六人の伯父の家での居候生活は半年ほどで終わった。
母親と嫂の間がにっちもさっちもいかなくなったのだ。
神戸生れ神戸育ちで都会ぐらし、それも日本各地の出身者の雑多な集まりの満鉄社宅くらしには、因習陋習の類が全くなかった。
嫂の方はと言えば、中国山地の辺境に生まれ育ち、同じような環境の農家の嫁になった。田舎には田舎なりの暮らしのルールがあり常識があり破ってはならない何百年来の習慣がある。二人の間の対立は、大きく言えば二つの文化の衝突だったろう。
母親の笑顔が消え、物を言わなくなり、やがて神戸へ帰ると言い出した。
父親は伯父の家を出て、離れて暮らせる家を見つけた。
【二十八】
移り住んだのは酒造家の蔵である。「美也正宗」という銘柄の酒を造っていたのだが、太平洋戦争が始まった頃から廃業同然になっていた。祖父が生まれた家である。
その作業蔵といっても木造の建物の半分を仕切り、六畳ほどの広さの部屋が二つ造ってあった。手前が居間、奥が寝室である。
作業蔵の残り半分はヘギ板造りの工場になっていた。我が家だけでなく引揚者は他にもいて、三、四人の男たちが働いていた。
敗戦後、家を建てるといっても必要な材料が入手できない。屋根瓦の工事も動いていなかったので代用のヘギ板がよく売れた。
ヘギ板なら金釘も要らない。竹釘ですむ。
酒造の作業蔵だからもちろんのこと、天井などはない。むき出しの梁からある夜、兄のふとんの上に青大将が落ちてきた。
【二十九】
満州新京で住んでいたのは満鉄の社宅である。番地は新京市西広場露月町3丁目66の2。煉瓦造りの外壁を、白っぽくコンクリートで塗り固めた2階建て。中央に階段と各戸の台所口。玄関に連なる廊下がある4戸の住宅で同じ建物は4棟しかなく、近くの社宅は赤煉瓦の4階建て、階段が2つある全6戸の集合住宅だった。
この社宅には2畳の玄関の間があり、奥にペチカを取り巻いて8畳の居間、6畳の寝室、6畳の食事部屋と便所があり、食事部屋が台所につながり、台所の背中に野菜などの貯蔵庫があった。
居間の三角窓からのぞくと4メートル幅の道路で、それを左側に100メートルほど歩くと小さな公園と社宅の住人が共同で建てた共同浴場があった。
【三十】
週一回通っているリハビリテーション施設の理学療法士から、毎日できるだけ歩くようにと言われている。
そこで、努めて歩きに出るようにはしている。
マンションの北側面に沿って、乗用車2台がやっとすれ違える幅の道が通っている。
居住地に変わる五十年ほど前は、一面の畑や田んぼだった地域だから、当時の農道がそのまま簡易舗装されて住民の生活道になっている。所どころに畑のまま残っている土地もあって、季節ごとの野菜が植えられている。
知られているように、農地の方が宅地よりも税金が安い。
今日歩いてみると、そんな畑の道端に設けられたスタンドに、形のいい、つやつやとした蕪が四個百円で売られていた。
【三十一】
社宅の前の幅4メートルの道路が満鉄職員住宅の子供たちの遊び場だった。
六年生のお兄さんがリーダーで、五年生から一年生まで同じ人数・戦力になるよう2組に分かれる。
「戦艦・駆遂艦・水雷艇」は相手チームの戦艦を早く撃沈させたほうが勝ち。戦艦は駆遂艦に勝ち、駆遂艦は水雷艇に、水雷艇は戦艦に勝てる。味方の水雷艇が相手戦艦の背中に触れれば勝ちになる。
道路を100メートルほど離れて分かれると、判定役の合図でいっせいに建物の裏に回ったり、煉瓦塀にかくれたり姿をかくす。
相手戦艦を捜すのも大変だが、発見してからが激戦だ。護衛の駆遂艦、水雷艇をまず沈めなくてはならない。昼ご飯の後から始めて夕方まで駆け回ることもあった。
【三十二】
西広場国民学校に入学したのは、太平洋戦争が始まった昭和十六年である。二月の早生まれだったので、九年生まれと同学年になる。
チビの虚弱児童だったので、男女混合のクラスに入れられた。
入学式の記念写真には白系ロシア人の少女が写っている。どんな少女だったのか、まったく記憶に残っていない。
引揚げのとき、写真はみな乗船前に取り上げられたのだが、わが家では末っ子の妹のリュックに隠してもって帰った。
虚弱児童は週一回、太陽灯の光を浴びる。満州新京の冬は長く寒い。陽光を浴びる機会も少ないため、子供の骨が健康に育たない。
その対処法として、人工の太陽光を浴びさせる、という政府(?)の指示だったろう。終わると、生臭い味のヒマシ油を飲まされた。
【三十三】
社宅から歩いて15分ほどのところに「児玉公園(西公園)」があり、よく遊びに行った。
正門を入ると正面に児玉源太郎大将の銅像が建っていた。日露戦争の満州軍総参謀長で、台湾総督時代は現地の人気が高かった。南満州鉄道の創立委員長でもあった。
調べてみると公園は10万坪余、中央に潭月池、南側に夕陽ヶ丘、北側に野球場、陸上競技場があり、全満州の社会人野球大会や陸上競技大会、冬にはスケート競技やホッケー競技を観戦した記憶がある。
子供の頃には正門からはめったに入らなくて、手近な裏門や横門から入っていた。
小枝を拾って針を付けた木綿糸を結びつけ飯粒を餌に小魚を釣る。
父親も休日にはよくここで釣りをした。規則では釣りはご法度だったけれど。
【三十四】
友人や娘、息子、それに理学療法士から「毎日歩いたほうがいいよ」と言われている。
できるだけ歩くようにしているのだが、急に冷え込んだり、雨の日には歩く気持ちになかなかなれない。
外を歩かない日はTVで視た「足腰を鍛える運動」の真似をして足首や太股を動かしたり「スクワット」風に腰を上下させてはいる。
今日は暦によると旧暦の大晦日だが例年の三月中旬の気温という暖かさ。セーターを薄い方に着替えていつものコースを歩いた。
折り返し地点近くの道端に畑があり、野菜の販売ボックスが立っている。
自家栽培の白菜一株200円、大根100円、里芋(中5個入1袋)100円、蕪(5個)100円とあり、その他になんと、「新米5kg1500円」と貼り紙にあった。現物は見ていない。
【三十五】
松花江へ父親につれられて釣りに行ったことがある。父は満鉄職員だったので、満鉄の列車には無料で乗車できる職員パスを持っていた。そのパスで特急アジア号の2等車に乗った。アジア号は満鉄自慢の特急列車で、機関車は流線型の車体(名称「パシナ」)。
昭和十年代の初め頃の世界最速時速130キロ、平均時速85キロで走った。
釣り場は吉林市郊外の河原だったが、向こう岸がぼんやりしてわからなかった。
父が釣り上げたのは1メートル半もある雷魚。からだに紫がかった茶っぽい斑点があり、口はアリゲータのように大きい。帰って洗濯盥に入れたら、一回りしてやと入った。
その夜、フライにして喰べた。白身で淡白な味だったが、小骨が多くて子供には食べにくい魚だった。
【三十六】
新型コロナウィルスに感染して肺炎を発症する患者が、クルーズ船ダイヤモンド・プリンセス号とは関係なく、北海道から沖縄までの十三都道府県で見つかって今日2月22日までに108名になった。
新型の感染症の流行ということで思い出すことがあった。
満鉄の職員アパートに住んでいた国民学校三~四年の頃、季節は夏の終り頃だったと思うのだが、通りを一本隔てた満人住居区が燃えたことがあった。正確に言えば燃えたのではなく燃やしたのである。
理由はペスト患者が出たためである。“黒死病”と恐れられたペストはネズミに寄生するノミから感染する。そのため、感染住居区の回りはトタン板で囲まれ、ネズミを逃がさないようにして火が付けられた。
【三十七】
国民学校一年生に上った年の十二月、猩紅熱に被患して隔離入院させられたことがある。
猩紅熱は当時法定伝染病に指定されていて患者は強制入院させられた。
病室の外に看護師や医師の出入りする廊下があり、見舞人はその外の窓越しに子供を見守るようになっていた。
当時住んでいた社宅は消毒薬で真っ白にされ、友達の家も同じ目にあったらしい。
入院は一月ほどかかり、年明けての退院だった。退院する頃には病室をとびまわって遊んでいて、看護婦さんによく叱られた。
入院した時、送ってきた母は廊下越しに私の様子を見ていて、もう会えないと思っていたといった。
昨年孫が被患したが、家に居て薬を飲みながら一週間過ごしただけだった。
【三十八】
TVニュースを見ていたら、「芸備線の機関車が庄原駅を出たところで脱線転覆した」と言った。(中国豪雨の翌年だったか)
芸備線は広島と中国山地の備後落合を継ぐ鉄道線で、私は高校生の時、一年間甲立駅―備後十日市駅に乗って三次高校に通い、二年間は甲立―向原の間この鉄道にゆられ向原高校に通学した。当時は四輌連結で毎朝学生や通勤客、広島へ向かう一般客で満席だった。機関車はまだ蒸気機関車で、窓を開けていると石炭の燃える匂いと煤煙に襲われた。
車窓から眺めた朝夕の景色は今でも想い出すことができるし、なつかしい。なつかしさの中には友人・知人の顔もむろんある。
庄原には二十代の頃からの友人がいる。芸備線のその後を聞こうとしていたら無事復旧のニュースを新聞で知った。
【三十九】
昭和21年10月に父の生まれ故郷に満州新京から引き揚げてきた。
父は翌11月に母の実家のある神戸を訪ね、その後若い頃働いていた大阪・京都へ廻って帰ってきた。どうやら母と兄嫁の間の確執をさけるために働き口を探しにいったらしい。
農家の次男だった父は高等科を出るとすぐ大阪に働き口を求め、鉄工所の見習いに入った。そこで施盤の技術を身につけ、二十代の時には京都市電の修理工場に勤めていた。その頃の知人を頼っていったとおぼしい。しかし、大阪・京都での生活をあきらめた。
京都は戦時中、空襲にも見舞われず、仕事もあったようだったが、あきらめた。京都では育ち盛りの男児三人をとうてい喰べさせられない、と思ったらしい。敗戦時の食糧難はそれと判るほど深刻だった。
【四十】
週一回通っていたリハビリ施設が改築のため休業してしまった。再開は22年六月。
心配したケアマネージャーが、近所の施設を調べてパンフレット等資料をもってきてくれたのだが、どうも気が進まない。施設が狭いし、リハビリ用の器具も数少ない。利用可能な人数はせいぜいおおくても6~7名か。
閉鎖した施設は、小学校の講堂くらいの広さがあり、半分を常時二十名以上のデイサービスに、残り半分を午前と午後に分かれてそれぞれ二十名以上の利用者が集まっていた。リハビリ用器具の種類も数も多く、利用者はそれぞれ自分の好みに従って器具を楽しく使って廻る。顔なじみとは雑談を交わしながら、という楽しみもあった。
つまり、そこはリハビリ施設であり、半日を楽しく過ごす無二の場所でもあったのだ。
【四十一】
毎日、できるだけ歩くようにしている。距離は1500メートルほど。杖を突き突きよたよたと歩いている。
この五、六年の間に古い家屋が壊されて四軒の新築に変わったりして人家が増えているのだが、まだ畑のまま残っている土地もありそこに農家の自販所がある。
この二、三日覗いていると、小袋に米を入れて売っている。米の銘柄は「キヌヒカリ」二合入りで一袋100円。一升500円、一斗5000円、四斗一俵二万円という計算だから、市販の上等米と同じくらいの値段だろう。
のどかな景色だなと思っていたら、今日は一変していた。張り紙がしてあり、小銭30円入れて六袋も持っていった女性がいたらしい。棒筒状のお金入れには、監視鏡がついているのである。
【四十二】
リハビリ施設の送迎車にいつも同乗する女性がいた。昭和3年生まれということで、腰が曲がり、杖をついて歩いておられたが大変お元気で、耳が少々遠く、目が見えにくくなっているとおっしゃるが、身装いもきちんとしていて93歳というお年にはとても見えない。
「あなたのお歳で大学出はめずらしい」とおっしゃったが、ご本人は早稲田鶴巻町の生まれ育ちで、大隅講堂の階段が遊び場だった。
昭和17年に当地に嫁いでおられたお姉さんを頼って疎開してきてそのまま住みつき、結婚もしたのだ、と。
独り住まいだが近くに孫夫婦がいて、よく面倒を見てくれる、とおっしゃる。
独居老人といわれるが、ひとそれぞれのくらしが当然あるのである。
【四十三】
父の古い写真が残っている。
大黒頭巾をかぶり、大黒さんそっくりの衣装を着て自転車に乗っている。二十歳を二つ、三つ過ぎているだろうか。若い。
この頃父は、どこかの鉄工所で施盤工として働いたはずである。
広島の備後地方の山村で生まれた。毛利元就の本貫の地吉田と、義士伝の赤穂藩主浅野長短夫人の実家があった三次市にはさまれた人口三千人ほどの小村の農家の次男である。どういう伝手があったのか、小学校高等科を出てすぐ大阪の鉄工所の見習いに入った。
以来、満州から引き揚げて帰郷するまで、施盤工として世を渡った。引き揚げ時は満鉄の鉄道工場の工員で、新京の工場から吉林工場に移って三か月程度の頃、ソビエトの満州侵略に襲われたのである。
【四十四】
昨日の雨が振り止んで、朝から快晴なので歩きに出た。
いつものコースを歩きながら見慣れた人たちとすれちがう。お二人とも杖をついているご夫婦や買い物袋をさげた女性、自転車で駆け抜ける母娘。
楽しみはコースの半道ほどにある農家の自販所。今朝は何を置いてあるかなと覗いてみると、この時期らしく「餅米」があった。一袋に二合入ったビニール袋が7~8袋。一袋100円である。
中学生の頃、父親が田んぼも作っていて、三畝ほどは餅米も植えていた。その収穫米がお正月のわが家の餅になった。
白い餅だけでなく大豆やよもぎ、黍を入れた餅も搗く。いまでも黍餅は大好物だが、残念ながら売っている店がない。
【四十五】
満州から引き揚げ後、父は伯父(父の長兄)の仕事を手伝っていた。伯父は木材の売買と製材業を家業にしていた。敗戦直後だったから復興のための需要は高く、直径2~3寸の丸太から高級建材まで飛ぶように売れた。
やがて父親は伯父の手元を離れて自立、積極的に一山分、丸ごと買うというような大胆さも見せた。
そんなある日、壊れてディーゼルエンジンを拾ってきた。それを一週間もかけたろうか、修善して動くようにした。そしてそのディーゼルを動力にして製材も始めたのである。
仕事は絶え間なくつづいた。県道に面した庭つきの古家を買いとり、住み家と仕事場にした。
そのおかげで私と妹が上京、大学へ進学することができたのである。
【四十六】
風が強かったが今日もいつものコースを歩いた。杖を突いていてもからだがふらつくので、強風の日には転ばぬよう気をつける。
いつものように農家の自販所をのぞく。
今日はうるち米キヌヒカリと餅米に「菊イモ」が加わっていた。値段は相変わらず100円である。この自販所をのぞくのが楽しみで歩けているようなものだ。
コースを戻ってきて石彫の夫婦神の前まできたら、隣の駐車場の入り口で板棚に緑の野菜が置いてある。
水菜、からし菜、わさび菜、小松菜、そして赤大根。値段はどれも100円。運よくポケットに百円玉が4~5枚入っていたので、赤大根を一本手にした。
赤大根は1ミリほどの薄切りにして、買い置きの合わせ酢に漬け込んだ。
【四十七】
初めての外国旅行の行き先はハワイだった。シカゴに本社のある出版社の日本支社に勤めることになり、最初の編集会議がホノルルのホテルで開かれたからである。
1972年のことで、当時は1ドルを168円と計算して予算を立てたと記憶している。
海岸に近いホテルに泊まったのだが、ベッドではなかなか寝つけなくて、翌日はぼんやりした頭で会議という日が三日続いた。
シカゴ本社が出している15巻物の子供の読み物全集で、すでにイタリア語版、スペイン語版が出ていて、日本語版と同時にフランス語版の企画も進んでいた。
その年の十月には最後の校正刷を見るためにテネシー州のキングスポートに一ヶ月ほど滞在した。同名の印刷会社があり、世界最大の印刷会社といわれていた