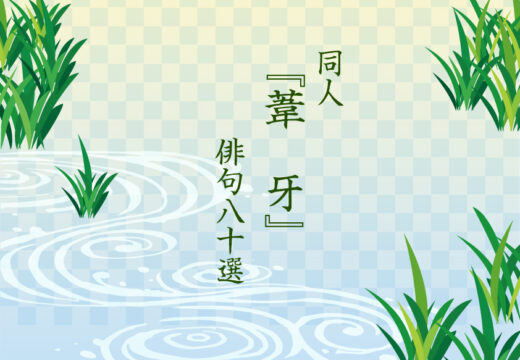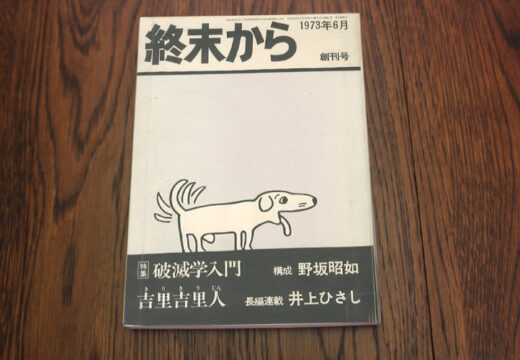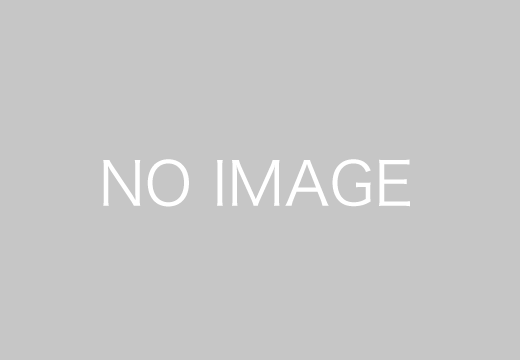|
2009年09月30日
|
|
『食の大正・昭和史—志津さんのくらし80年—』 第四十四回 月守 晋
●大阪庶民の“うまいもん” 蝶子の父親種吉が住まいのある路地の入り口で商っているのは牛蒡(ごぼう)、蓮根、芋、三ツ葉、蒟蒻(こんにゃく)、紅生姜(しょうが)、鯣(するめ)、鰯などを揚げて1銭で売る1銭天婦羅である。 味がよいので評判だったが元手の7厘には炭代や醤油代が含まれていず損をしている。 こういう書き出しで始まる織田作之助「夫婦善哉」は昭和15年に発表されたものだが物語の時代は大正から昭和10年ごろまでだろうと思われる。 織田作之助は昭和14年から敗戦直後の22年2月に喀血死するまで9年という短い期間だったが多くの作品を発表して人気作家であった。 大阪で生まれて府立高津中、三高へと進んで小説を書き始めるが大阪の庶民のくらしを題材としたものが多くそれが評価され人気を呼んだのである。 神戸と大阪では同じ関西といっても都市としての成り立ちも歴史も違うので、食生活を含めてくらしぶりはずいぶんと違っていたろうと思われる。 志津さんが初めて家を離れて働き始めた他郷で出会った食生活がどのようなものだったのか、織田作品から探ってみようというわけである。 「夫婦善哉」は法善寺横丁に現在も実在するぜんざい屋で、織田作品は昭和30年、森繁久弥の柳吉、淡島千景の蝶子、豊田四郎の監督で映画化されこの年の日本映画ベストテンの2位に選ばれた。 梅田新道の安化粧問屋の息子である柳吉が“うまいもん屋”として蝶子を連れてゆくのは戎橋筋そごう横のどじょう汁と皮くじら汁の「しる市」、道頓堀相合橋東詰のまむし(うなぎ)の「出雲屋」、日本橋(大阪では「ニッポンバシ」と発音する。東京は「ニホンバシ」)「たこ梅」、法善寺境内の関東煮の「正弁丹吾亭」、鉄火巻と鯛の皮の酢味噌の千日前常盤座横「寿司捨」、その向かいのかやく飯の「だるまや」などである。 これらはたぶん、作者自身の好みでもあったろうか。 織田の小説にこうした食べ物やその値段が子細に語られるのは「これだけは信ずるに足る具体性」の表現だという作者の信念を作品「世相」を引いて青山光二が解説している。 ともあれ、織田作品から志津さんが13歳から18-19歳ころまでの大正13年-昭和5年ころに大阪市中で目にすることのできた食べ物を拾ってみよう。 ( )内は作品の題名 *ミルクホールの3つ5銭の回転焼(「雨」) 志津さんにはこのような大阪の“うまいもん”を目にする機会もなかったろう。 商人の街である大阪では朝は前日の残り飯を粥(かゆ)にして食べ、昼に魚などの副食つきのたいた御飯、夕食に昼の余り物で茶漬けを食べるというのが一般だという(『上方食談』石毛直通)。 志津さんも朝晩は粥か茶漬け、昼はせいぜい煮豆などをおかずに台所で食べさせられていたのだろう。 |
食の大正、昭和史