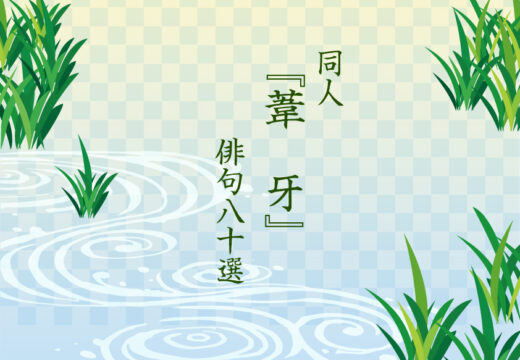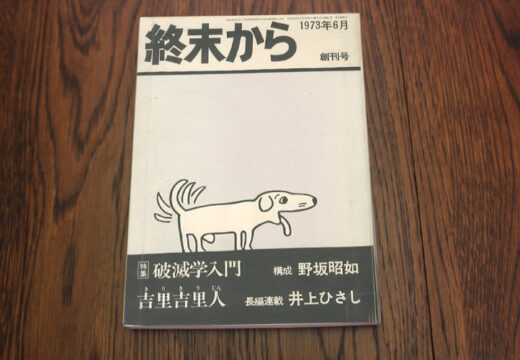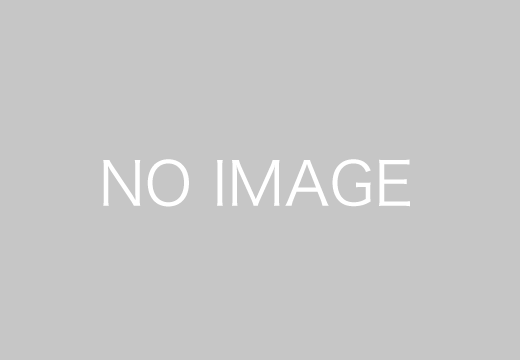|
2009年09月25日
|
|
『食の大正・昭和史—志津さんのくらし80年—』 第四十三回 月守 晋
●行儀見習の奉公(5) 志津さんの口から“座敷牢”という衝撃的なことばが出てきたのは行儀見習の奉公に出ていたころの話を聞いていた時ではなく2、3日後に駄菓子をつまみながらお茶を飲み雑談に興じていた時のことであった。もっともお茶を飲み菓子をつまんでいたのは聞き手とまわりにいた人間のほうで志津さんは甘い物嫌いのうえにお茶を決して飲まなかった。 志津さんの甘い物嫌いは子供のころからのことだったし、水しか飲まなくなったのがいつごろからのことなのかいっしょに暮らしていた子供たちも気づいていなかったのである。 神仏などに願いごとをし、その願いごとが成就する(かなう)まで、たとえば自分のいちばん好きな物を口にしないことを誓う「願かけ」が昔はよく行なわれていた。「酒は生涯1滴も飲まない」とか「お茶をたつ」と誓う行為を「酒だち」「茶だち」と称して周囲も「そんならしょうがないや」と付き合いの悪いのを容認したのである。 志津さんが何か願いごとがあって「茶だち」を始めたのか、それとも何かをきっかけ—–、たとえば身近な人の死などをきっかけにお茶を飲むことをやめてしまったのか、それはわからない。しかし志津さんは死ぬまで温かいお茶を飲むことはしなかった。 話が妙な方向にそれてしまったが、しかし、絹の反物を商う商家に「座敷牢」などというまがまがしい部屋が造られるなどということがあったのだろうか。 映画の中では見たことがある、という人はいるだろう。時代物の映画では藩政改革をこころざす跡継ぎの若殿を側室と手を組んだ悪家老が策略をめぐらせて狂人に仕立てて、格子で囲った一室に閉じ込めてしまうというストーリーだ。格子の囲いには小さな出入口が1つついていて、厳重に鍵がかけられ番人に見張られている。部屋は格子の外の障子を立てられると一日中、日光が入らず薄暗い。 「座敷牢に入れられた時は、障子の桟を数えていた」と志津さんはいうのである。 昔の日本家屋には「ふとん部屋」という小部屋があった。使われなくなった古ぶとんや臨時に雇った手伝いの人に使わせる予備のふとんを収納してある長3畳とかせいぜい5畳ほどの部屋である。たいてい女中部屋の隣りとか表座敷から離れた家屋の裏手の薄暗い隅にあった。 志津さんのいう“座敷牢”はこういう小部屋だったのかもしれない。志津さんがこうした部屋に閉じ込められた理由もわからない。が、たぶん、志津さんの“強情”が原因の1つだったかもしれない。これは理不尽と思うとテコでも動かないところが志津さんにはあった。そんな志津さんを「少しこらしめてやれ」とふとん部屋に押し込めたのかもしれないのである。 自由学園の創始者であり、雑誌「家庭之友(5年後「婦人之友」と改題)」の創刊者でもある羽二もと子(明治6年-昭和32年)は女性のための啓蒙書を数多く書いているが、その中に『女中訓』がある。「訓」は「教えてわからせること」で、つまり「どうすればりっぱな女中になることができるか」の指導書である。 大正元年に書かれているが、つまりは働いている家のために腹を立てず、他人をうらやまず、時間をむだにせず、頭を働かせて要領よく、主人やまわりの人に好かれるように努めなさい、ということである。 こころざしに違(たが)えて女中奉公をしていた志津さんはむろん、こんな模範的な奉公人ではいられなかったのだ。 |
食の大正、昭和史