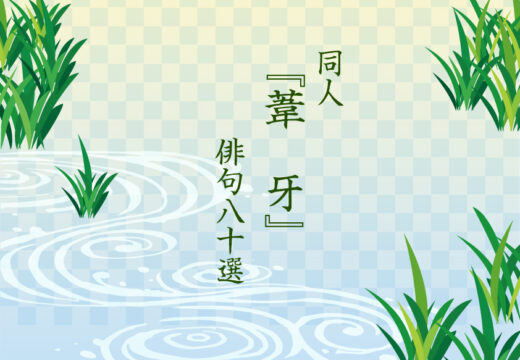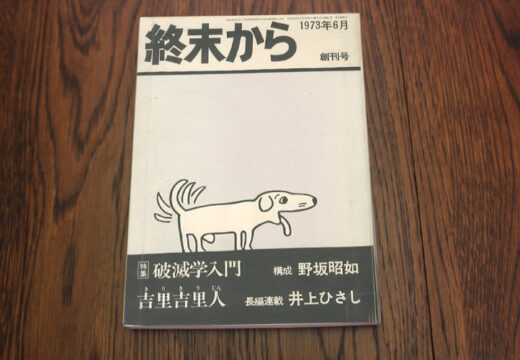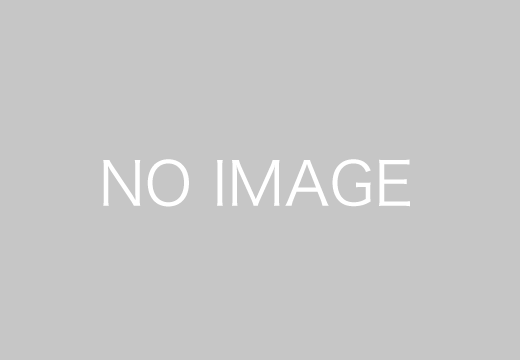|
2009年01月21日
|
|
『食の大正・昭和史—志津さんのくらし80年—』 第十四回 月守 晋
養母みきの内職だったマッチ箱貼りの手伝いをすると、毎日小遣いをもらうことができた。たいていは1銭か2銭で、長田神社の祭日など特別な日には5銭もらえた。1銭は1円の100分の1だが、当時の1銭はなかなか実力があって前にも紹介したように1銭にぎって駄菓子屋に行けば買えるものはいろいろあった。子供はその中から、今日は何を買おうかと知恵を働かせたのである。 ちなみに大正3年、森永製菓が売り出した20粒入りの紙サック入りキャラメルは10銭、大正10年発売の江崎グリコのハート型キャラメル・グリコは10粒入り5銭だった。チューインガムも米国リグレー社製の「ダブルミント」「スペヤミント」2種が、クリスマスと正月贈答品として大正4年に1包10銭、進物用20包入り1円75銭で売り出された。新聞の広告にはチュウインガムには「噛(か)み菓子」と説明がついている。 甘い物があまり好きではなかった志津さんは、子供の集まる駄菓子屋ではなく近所の酒店によく行った。この酒店では店前に関東煮(かんとだき)の鍋が置いてあり、神戸港で働く沖仲士や港内の作業員が1日の仕事帰りに立ち寄って冷や酒を飲みながら小腹をみたしていた。 「関東煮」は関東風の「おでん」のことで、関西で「おでん」といえば「こんにゃくの焼き田楽」のことなので区別して「関東煮」と呼ぶのである。 関西と関東では煮込むタネにも違いがあってクジラの舌(サエズリ)、同じくクジラの脂身・いり皮(コロ)、棒天(ちくわのような揚げ物)、タコの柔らか煮、そしてジャガイモは関西の関東煮に特有のもの。 関東のおでんにはちくわぶ、はんぺん、イカが入りじゃがいもではなく里芋になる。 「おでん」は「田楽」の御所ことばで「お田楽」の略であり、やがて民間にも広まったと食物史には書いてある。こんにゃくの田楽は江戸時代の元禄年間(1688-1704)に屋台が現われ、8代将軍吉宗の享保年間(1716-1735)には味噌田楽が現れた。その後それが味噌煮込み田楽に変わっていったのである。 さらに醤油汁で煮込む「江戸おでん」の出現は幕末になってからだという。 志津さんがお八つ代りに食べたのは好物だったジャガイモで、2個串に刺してあるのが1銭から2銭だった。ジャガイモのほかには三角の厚揚げも食べた。 田辺聖子の『道頓堀の雨に別れて以来なり』は6年間にわたって中央公論誌上に連載された豊醇な現代川柳・川柳作家史だが、その中で川柳作家たちの集まった上燗屋(じょかんや)のことにも触れている。この場末の一杯飲み屋の関東煮はこんにゃく、厚揚、豆腐、卵が大鍋でぐつぐつ煮られていたと説明されている。 また「大阪の古いかんとだき屋、今でもあるミナミの<たこ梅>」では川柳の同人誌「番傘」が創刊された大正2年当時、こんにゃく1つが2銭、タコの足が1串10銭だったとも。 それにしても、港湾の仕事帰りの沖仲士のおっちゃんや兄ちゃんに混じって、ジャガイモの串をかじっている小学生の女の子とは、実際に目にしていれば、声をあげて笑いたくなるような、オイオイと声をかけてやりたくなるような、珍妙な光景ではなかろうか。 京都の町医者の子だった松田道雄さんは、知人の家のおない年の子供が動物園で屋台店の餡パンを買ってもらって食べ、1日のうちに疫痢で死んで以来、父親の食品管理が一層厳重になり「患家からもらうカステーラ、人形の形をしたビスケット、田舎から送ってきたモロコシの粉で母がつくる団子、熱湯をかけてこねたはったいの粉ぐらいしか」お八つにもらえなかったと書いている。 |
食の大正、昭和史