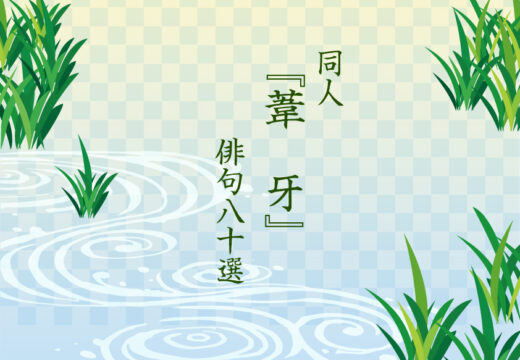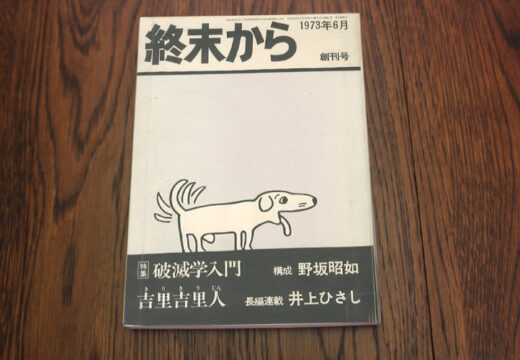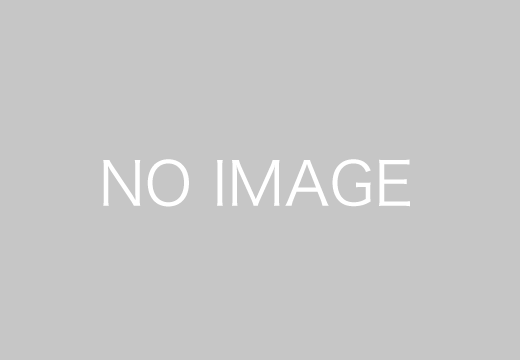|
2009年10月28日
|
|
25. 「背に負う板チョコが、一枚一枚、鋼チョコレートと思えたそうだよ」 引揚者たちはそれぞれに縁故のある土地に帰り、親兄弟・親類縁者・友人知己を頼って生活の再建を始めるわけですが、それは容易なことではありませんでした。 戦争末期の昭和20年3月から始まり敗戦直前の8月13日まで、広島・長崎両市への原子爆弾攻撃をふくめ、全土の60都市が米空軍の空襲にさらされ、約260万戸の家が焼かれ1,300万人が住居を失っているという状況でした。 もちろん工場などの生産施設も灰になり、ろくな働き場所も残ってはいません。そんな混乱のさ中にある祖国に帰ってきた引揚者・復員軍人たちは、ただ眠る場所を見つけ食べていくために大変な苦労を強いられました。「顔の中の赤い月」の主人公北山年夫は1年ほど前、南方(タイ、ビルマ、ラオス、スマトラ、ボルネオなど)の戦線から復員して、東京駅近くのビルディングの5階にある知人の会社に席を置いています。 同じビルの廊下をへだてた別の会社に堀川倉子という女性が勤めていて、北山は彼女に関心を寄せています。倉子は南方の戦線で一つ星(二等兵、最下級)の兵士として召集された夫を戦病死で失った戦争未亡人です。 著者の野間宏は敗戦前の軍隊がどのようなものであったかということをつぶさに描いた重厚な作品『真空地帯』をはじめ、戦中戦後の時期とその中で足掻きもがき苦しみながら生き抜いた日本人の姿をとらえた数多くの秀作を残しています。 「顔の中の赤い月」にも敗戦後数年を経たばかりの首都東京の生活が反映しています。北山の復員仲間の山沖には定職がなく、闇の商売で生計を立てています。扱うのは板チョコで、1枚を7円50銭で仕入れて8円50銭で田舎の雑貨屋に置いてくる。差し引き1円の儲けで月3千500円ほど稼ぐというのです。その山沖も商売を始めてすぐには売り込むべき土地を間違えて1枚も売れず、冒頭に掲げたようなつらさを味わったというわけです。 敗戦後の闇市場には、進駐軍から横流しされたハーシーとネッスルの板チョコが出回っていました。その一方でさつま芋から作ったグルコースや薬用カカオバター(座薬などに使う)の副産物のココアで作ったまがい物の“グルチョコ”と呼ばれた品物が出回っていました。山沖が扱っていたのは多分、この“グルチョコ”なのでしょう。 |
チョコレート人間劇場