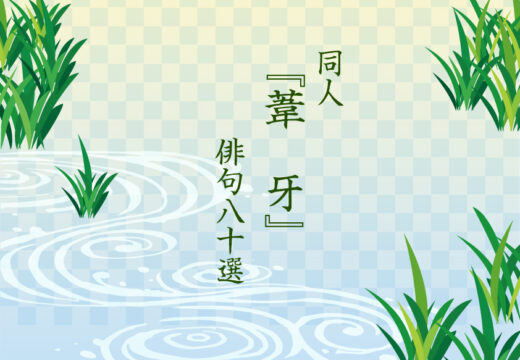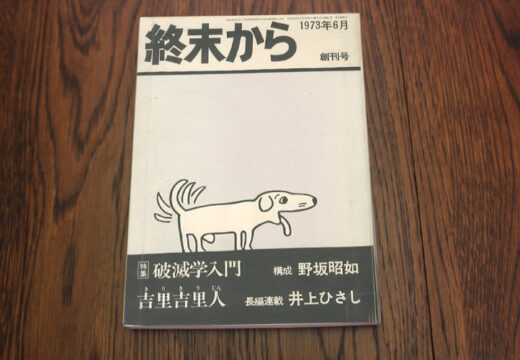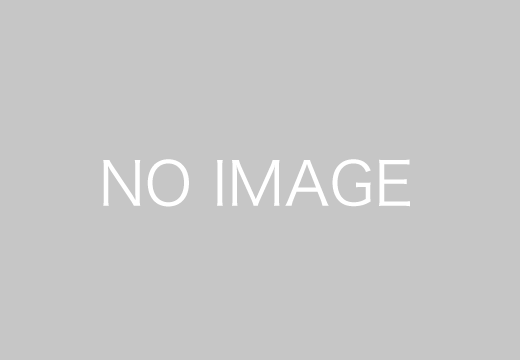|
2009年12月16日
|
|
28. 「私は、夫にチョコレートをもらうたびに、私をよその女でなくしたことへの、夫のお詫びの贈り物だと思っている」 全部で16のエッセイがまとめられていますが「結婚してもうじき二年、という秋から、もうじき三年、という秋までのあいだに書いた」と書いています。 著者も著者の夫も、でるつもりじゃなく海にでた、その航海の記録だ、と。 結婚生活は「大きな公園のそばの小さなマンション」で始まった。エッセイの最初の1篇もその公園とのかかわりが語られています。結婚して変わったことのひとつに「推理小説を読む」ということがあって、「結婚してからとりつかれたように」読むようになり、「いまでは、推理小説がなければ妻生活というものはやっていられない、と思う」ほどなのです。 公園の大階段で推理小説をとりつかれたように読むのは推理小説は「最後にちゃんとけりがつく」からで「(私が)たぶん、けりのつかない場所に不慣れだからなのだろう」と。 既婚者は新婚のころの自分を改めて思いかえしてみざるを得ないでしょうね。同じ家に一緒にくらしはじめて初めて相手に感じられる異和感があり、それを説明してわかってもらおうとしても相手はなかなか理解してくれない。「けり」はなかなかつかないものです。 『いくつもの週末』には1篇ごとに、こうした読む者を危険な淵に誘い込む数行がふくまれています。解説の井上さんもこの本は「私たちを落ち着かなくさせる」と書いています。 たとえば次のような文章。 「二人はときどき途方もなく淋(さび)しい」―「月曜日」 「色つきの世界というのはたぶん、この依存と関係があるのだろう」―「色」 「一時の気の迷い、は、我が家における冗句(じょうく)であり真実であり結論であり、…」―「風景」 冒頭に掲げた文章も「…よその女でなくしたことへの、夫のお詫び…」、にドキッとしませんか。 (『いくつもの週末』集英社文庫/‘01年) |
チョコレート人間劇場