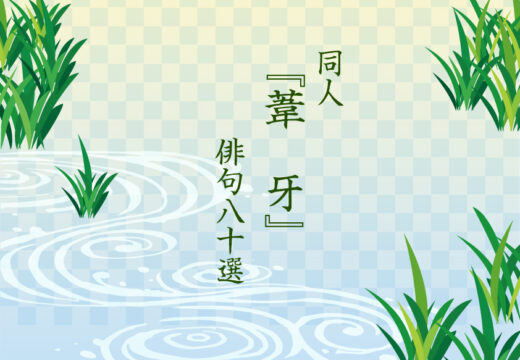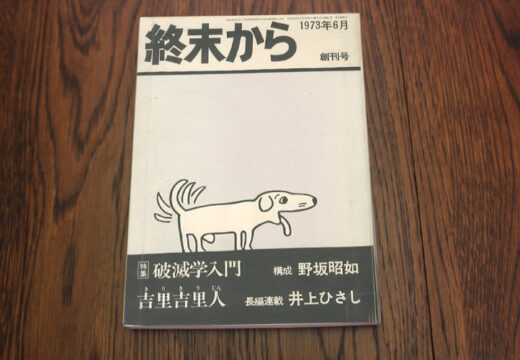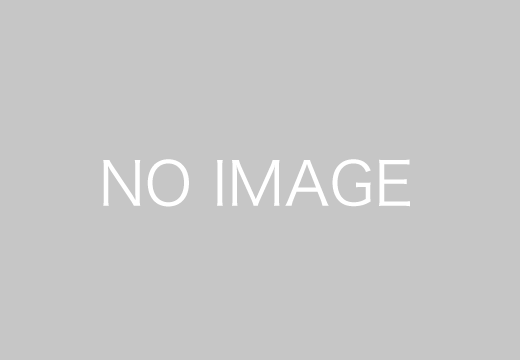|
2008年11月28日
|
|
6. おふくろはさよならと言うと、陽の降りそそぐ、小石で舗装した道路を戻って行った。 「疎開」という言葉があります。いま、60代の後半以上の年齢の世代ならば、ご自分が体験なさった方も多いでしょう。岩波国語辞典<第四版>には「敵襲・火災などによる損害を少なくするため、集中している人や物を分散すること」と解説されています。 太平洋戦争(1941(昭和16)-45(同20)年)中の日本では44(昭和19)年8月から学童の疎開が始められ、8月22には沖縄からの疎開船対馬丸がアメリカの潜水艦の魚雷攻撃を受けて沈没し、学童700人を含む1500人が死亡しています。疎開中にアメリカ空軍の都市空襲によって両親を失った学童もありました。 ヨーロッパでは1939年9月、ドイツの陸・空軍がポーランドに侵攻し第2次世界大戦が始まりますが、イギリスではその前年の秋、学童にもガス・マスクが支給されました。 1950年代の“怒れる若者たち”を代表するイギリスの作家アラン・シリトーは、ロンドンから180km北西の、ノッティンガム市で生まれ育ちましたが、39年9月、3人の弟や妹とともに疎開を経験します。28年生まれのシリトーはこの年10歳、父親は戦争のおかげで失業から救われたばかりでした。 疎開先はノッティンガムの北、27マイルほど離れた炭鉱町ワークソップで、疎開当日は「子供を運び出すために町じゅうのバスが調達された観」があったと回想しています。 きょうだい4人は4軒の家に割り当てられましたが、シリトーを引き受けてくれたのはサンドヒル街32番地のカッツ家で、主人はリヤカーに野菜や果物をのせて売り歩く行商人でした。夫妻は陸軍の少年兵になっている16歳の息子の部屋を使わせてくれました。 「昼食時間に遅れないように帰宅すること」というのが唯一のルールだったこの家で、シリトーは「新しい気持ちのいい生活に夢中になっていた」といいます。毎土曜日にはお小遣いを3ペンスもらい、アルバートというベッドを分け合う疎開仲間もできます。数週間後、弟妹たちにも再会しますが、みんな土地の人の援助や母親の送金のおかげでノッティンガムを出たときより、小ざっぱりした服装をしていたのでした。疎開バスに乗るとき、シリトーの持ち物といえば鞄と着替えのシャツ1枚、『モンテクリスト伯』の本1冊、紐の切れたガス・マスクのケース、だけの着たきり雀だったのです。 その後彼は学校にも通わせてもらい、国語の作文で4ペンスのほうびをもらったこともありました。 カッツ家でシリトーは良い経験も悪い経験も味わいますが、ここでの生活は3ヶ月で終わりました。 シリトーは15歳から働き始めますが、就職して自転車を買った彼はある日曜日、ペダルを踏んでカッツ家を訪れ、ミセス・カッツにシチューをふる舞ってもらいます。 1957年『土曜の夜と日曜の朝』によって作家として認められたシリトーは疎開した年の28年後、雑誌にこのカッツ家での生活の様子を語ったエッセイを発表し、それがきっかけで、72歳になっていたカッツ夫人と文通によって再会します。ミスター・カッツと死に別れた夫人は再婚し、ミセス・ホールと姓を変えていましたが2度目の夫にも死別して1人ぐらしの身になっていました。それでも、陸軍少年兵だった息子が無事帰還し、彼女は19歳の孫娘を持つ“おばあさん”になっていたのでした。 日本の学童疎開については、多くの人が回想記を書いています。当時の子供たちがどんな日々を過ごしたのか、あなたにも知ってほしいと思います。 参考 : 『私はどのようにして作家となったか』 アラン・シリトー/出口保夫訳/集英社 |
チョコレート人間劇場