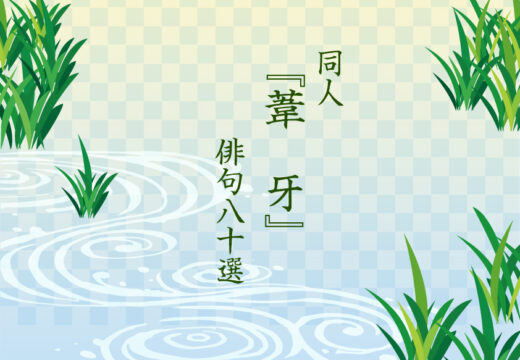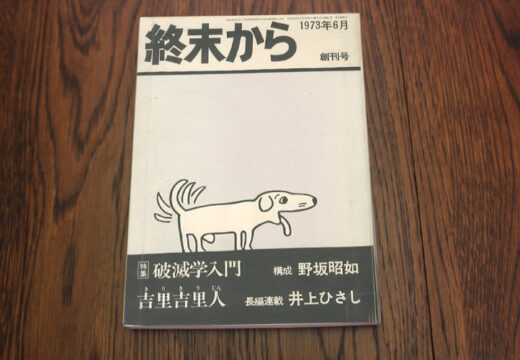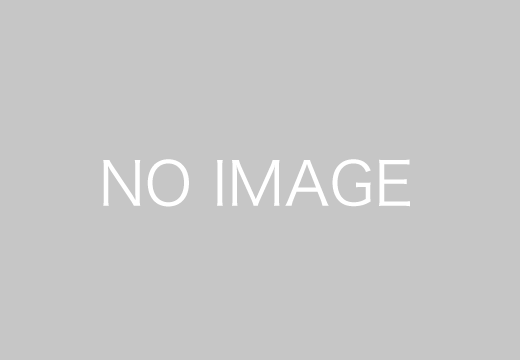|
2009年08月05日
|
|
『食の大正・昭和史—志津さんのくらし80年—』 第三十七回 月守 晋
●食の東西交流 - 関東大震災(5) 地震の被災者が何よりも困ったのは食べ物と飲み水が苦労をしても手に入らないことだった。 震災の状況が明らかになった直後から全国から救済品が続々と送られてきた。救済品は東京では芝浦の埋立地に集められ、府内各区役所に配給されることになっていた。しかし実情は芝浦の倉庫はほとんど焼失し、輸送手段もないまま野天積みされていた米穀類は腐敗し、馬鈴薯は芽を出すという始末だった(10月5日「大阪朝日新聞」)。 震災の年の前年に早稲田大学の文学部仏文科を休学したままこの年に中退していた井伏鱒二は、大学に近い下戸塚の下宿屋の2階で地震に遭った。地震後、茗渓館というその下宿屋では玄米しか売らないからといって、ビール瓶に入れた玄米を棒で搗(つ)かせて各自の食べる分だけ精米させたという。 太平洋戦争(1941, 12, 8-1945, 8, 15)の末期、苦労して手に入れた闇米の玄米を1升瓶に入れて棒で搗き、5分米ぐらいに白くして食べたという話を聞かされたことがあったが、この精白方法は大正時代からすでに行われていたことがわかる。 地震後7日目に井伏鱒二は中央線で郷里の広島県深安郡加茂村に帰るのだが、途中、甲府駅で空豆を1袋、上諏訪か岡谷ではあんパン1つと空豆1袋、中津川駅で大茶碗に味噌汁と握り飯をもらって息をついている(『私の履歴書』日本経済新聞社)。 震災後、関東・東京から多くの人びとが関西・大阪に移り住んだ。そういう人びとの中に江戸流の握りずしの職人がいて、これまで箱ずしや鯖ずしが主流だった上方に握りずしが流行りはじめたといわれている(『日本食生活年表』西東秋男/楽游書房など)。 鯖ずしの本場は京都で比良や比叡の山坂を越えて運ばれてきた若狭の鯖が使われた。この鯖は生鯖ではなく浜で塩をした塩鯖だったが流通事情が良くなった現在は生鯖を京都の各店で塩切りして用いるようである。 箱ずしは四角な木枠にすし飯をつめ、その上に卵焼き、鯖の身の薄切り、赤貝やとり貝などの貝の身、きくらげなどを置いて中ぶたで押さえる。2段にする場合は中間にシイタケやかんぴょうの煮つけをみじん切りにして敷き並べる。使う具は何でもいいのだが、魚のすり身を混ぜ合わせて焼いた卵焼きは欠かせないものである。 こう書いてくるとわかるように、ずいぶんと手間と時間がかかるものである。それに比べて東京風の握りずしは酢飯が馴れるまでといってもさほどの時間ではない。この酢飯の上に魚の薄切りをのせ握ればいいのだから上方のすしに比べればずっと手軽である。それにしても店をかまえているすし屋で握ったはしから客が口に運ぶようになったのは大正12年の大震災以後の話で、屋台店のマナーが店がまえのすし屋に持ち込まれてしまったためだという(『すしの本』篠田統/岩波現代文庫)。 震災でやむなく緊急避難のつもりで関西へ移住した谷崎潤一郎は東京日本橋の生れの東京育ちで、濃い味の関東風の味付けになじんでいたのが関西に住むようになってからこぶ出しの利いた薄味の京都風の味付けでなくてはならなくなった。谷崎は以後晩年まで関西に33年間住むことになるが、おいしい物好きだった谷崎を関西に引き止めた要因の一つは関西の味だといえるかもしれない。 「料理の味は西から東へ移動する」という(『食味往来』河野友美/中公文庫)。また、「京都の味は“料理屋の味”として、大阪の味は“庶民の味”として東京へ流れる」ともいう(同書)。さらに、「上品にできないものは東京に進出しにくい」といい、「タコ焼き」をその例にあげている。 大勢の人が移動した関東大震災後には人と共に様々なものが西から東へ、東から西へと移動したに違いない。 【関東大震災発生後に次のような忌わしい事件が起きていることをわれわれは忘れるべきでない】 ・ 朝鮮人・中国人の大量虐殺 |
食の大正、昭和史