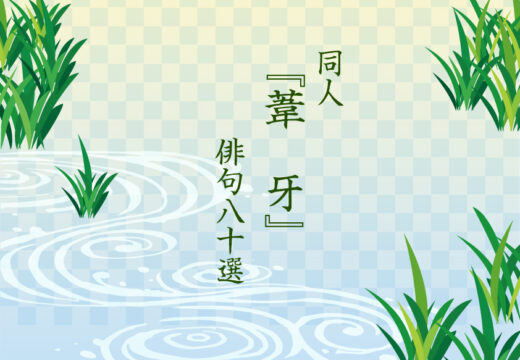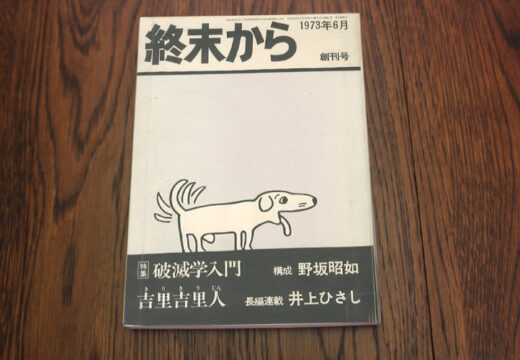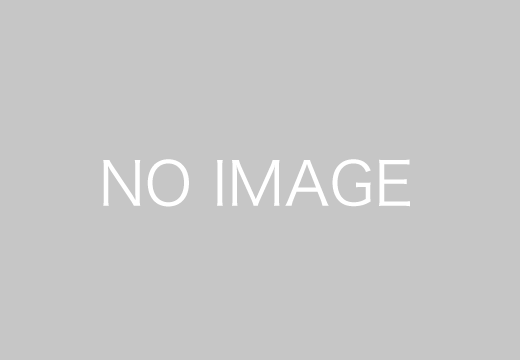|
2009年07月02日
|
|
『食の大正・昭和史—志津さんのくらし80年—』 第三十二回 月守 晋
●コメの飯 料理本の紹介から野生の小鳥を食べる食習慣へと、話が少々横道にそれてしまったけれど、志津さんの生まれた明治末年頃(志津さんの生まれ年は44年)にこの世に生をうけた人びとの思い出、回想録などを読むとこの時代の人たちは大人も子どももたくさんの米の飯を食べていることに驚かされる。 『[新編]十代に何を食べたか』というタイトルの本がある。(‘04年平凡社社ライブラリー/’84年 同じ書名で未来社より刊行)。 この本には志津さんの生まれ年と前後して生まれた数人の人びとの想い出話が収録されている。 歴史学者(考古学)の樋口清之さんは1909(明治42)年奈良県生まれ。「米主食(それも朝は粥(かゆ)、昼は麦飯、夜はその麦飯に粥をかけたもの)が農村では普通」で「豆や豆製品(高野豆腐、湯葉)が庶民の常食」だったという。 「動物蛋白が極度に少な」く「山菜野菜の類が極めて多」くて動物蛋白といえば「河にいる淡水魚やシジミが中心」だった。 樋口さんが子どもの頃の奈良平野では冬には隣の和歌山県から「クジラの生肉」を売りに来たし、県内でとれる「牛肉よりもシカ、イノシシの肉を食べた記憶の方が多い」と述べている。 丸岡秀子(婦人問題評論家)さんは1903(明治36)年長野県生まれ。「野沢菜だけをおかずにごはんを何度もお代りした」という。ただし、1か月のうち1日と28日には塩鮭の切り身か干しイワシが1匹ついた。 10代の後半に佐久郡の農村から長野市の女学校に進み寮に入った。「“ライスカレー”と片仮名で献立が書かれた」物に初めて接したのはこの寮で、大皿の中の固い物が牛肉というものであることを知る。そして「割り合いに固くて、それほどおいしい物でもない」と思ったのである。 大釜で炊くご飯がおいしくて、みんな「三杯飯は普通で、四杯も五杯も食べる友人もいた」し、丸岡女史自身も「四杯目にも遠慮なく出し」と旺盛な食欲を充たしていた。前回に引用した小島政二郎『舌の散歩』には、「年のせいか間食(あいだぐ)いをしなくなったら、テキ面にソバとかスシとかを食う機会がなくなった」と書いている。 ソバ1杯で昼食をすます、ということは現在の私たちのくらしではよくあることだが、小島政二郎と同じ時代に生きた明治人にはソバやスシはほんの小腹ふさぎで、その分、しっかり3度の食事にコメの飯を食べていたということだろう。 次の話はもう昭和に入って5年という頃だが、作家の青山光二がその当時の旧制第三高等学校生徒の食事情を回想している(『食べない人』筑摩書房)。 その頃、三高の東門の前の通りには飲食店が軒をつらねていて、そのうちの1軒、「青龍」が行きつけの店になった。青龍の食事代は16銭。壁に貼ってあるメニューから客は好きな料理を選んで注文する。青山はよくブリかカツオの味噌煮を注文したが、これに味噌汁と漬け物がついて、セルフサービスのご飯は何杯でもお代り自由で16銭だった。 青山自身は茶碗に2杯がせいぜいだったが運動部の連中にはあきれるくらいお代りをする連中がいた、という。 栄養士の近藤とし子(大正2年生れ)は「私の十代の頃は、日本人のほとんどは一日に摂るエネルギーの80%から90%は米で摂って」おり、米の蛋白質はリジンが足りないだけで蛋白価は78と高く、大豆やアズキで必須アミノ酸のリジンを補えば完全食になると述べている(前掲『[新編]十代に何を食べたか』)。 |
食の大正、昭和史