投稿日: 2010年1月16日
新たな出発
東京産業の経営破綻の噂がしきりに取りざたされていたとき、私はダイエーやニチリューに供給していたプライベートブランドについて深く考えなければならなかった。この項については2009/08/09の東京産業の経営危機と正栄食品工業の協力要請を参照されたい。アメリカでナショナルブランドに対するプライベートレーベル(日本でいうプライベートブランド)について疑問を感じ始めていた。日本チョコレート工業協同組合の共同事業として出発していた事業が組合員以外のメーカーである正栄食品工業株式会社から売上げの80%を占めるダイエー、ニチリュー向けのプライベートブランドを仕入れるとなると、日本チョコレートの存在理由がなくなるという危機感があった。
もう一つの問題点は、プライベートブランドという名称のもとにつくられた商品は果たして顧客にとって真に利益になっているのかという甚だ初歩的な疑問であった。チョコレート業界の最大イベントであるバレンタイン商戦で、バレンタイン屋が供給する「問屋ブランド」が幅をきかせる時代になってきたというパラダイムシフト
が起きてきたことである。本来のプライベートブランドの定義が失われてきたことに対する危機感であった。本来プライベートブランドの販売上のリスクは小売業である量販店(百貨店、スーパー、コンビニ)が持つはずのルールが、小売店側によって一方的に放棄され始めている。もう一つの危機感は、定番商品のプライベートブランドは中抜きが常習的にどの量販店でも行われるようになってきたことであった。これらの危機感は時代の変化によって、わが業界にもたらされたものであった。この「時代の変化」に私は違和感を覚えた。
しかし、熟考してみるとそれまでのプライベートブランドの開発方式はアメリカで行われていた方法と真っ向から逆のことをやってきたのではないか。日本の小売業が自らのもつ能力で開発したことのない分野を問屋の知識を利用してプライベートブランドを開発して来たまでのことで、そろそろその学習が終わって自力で歩み始めたまでのことではないか。マスマーチャンダイジングとマスセールの帰結するところではないか。美味なるもの、健康に確かなるもの、価値に見合う価格が本当に現在行われているプライベートブランドにあるのであろうか。量販店の販売リスクを極限まで抑えた数種類の問屋ブランドの台頭でバレンタイン商品の販売は美味なるものから遠く離れた商品になってしまった。
百貨店のバレンタイン商品の売場は地下の食品売場だけではなく、7階とか8階の特売場にも大きなスペースを割いて多くの有名無名のメーカーを集めて集客している。たとえばダイエーのバレンタイン商品の売場には800アイテム以上の商品が並べられていた。その数は年を追う毎に増えていった。さいわいダイエーは「バレンタイン屋」の商品は扱わない方針を貫いていたが、その他のスーパーの店頭にはバレンタイン屋の商品が溢れかえっていた。新宿「高野」のような専門店でさえバレンタイン屋の商品に侵略されていた。
なぜか。バレンタイン屋の製品を扱えば楽なのだ。いろいろの製品ラインが揃っているので、売れ筋の500円の商品は6種類、色替えが3種類あれば18種類の商品をたちどころに取扱うことが可能である。9月に概略数の注文を出し、12月にその注文数をアジャストすれば事足りる。そのうえ販売補助用具は周到に揃っている。考える必要がない。しかもリスクはほとんどゼロに近い。バイヤーは自分の購買権限を放棄してまでもバレンタイン屋の製品に力をいれた。
いわゆる「義理チョコ」なる商品についてはこのバレンタイン屋の製品が幅をきかせていた。この商品群は売れることは売れるが、バレンタイン当時の曜日がその年、その年で変わるたびに数量の増減があり読み切れない。ダイエーは1978年から返品のないバレンタイン商品 ー 本命にはあなたの手作りで(2009/02/08掲載)
を掲げて独自の季節限定商品を開発していたことが注目される。「義理チョコ」の販売に頼らなくても数字が読めた。この「割チョコ」は日本チョコレート工業協同組合のミルクチョコ(Deluxe)で購入者は必ずしも手作りチョコ用に買っている顧客ではなかった。
このような新しいプライベートブランドの開発をしていかなければ売場は陳腐化していくばかりであるという恐怖にとりつかれていた。しかし、このようなアイディアと売上げ実績が結びつくようなチョコレート開発はざらにあるものではない。どうしても新しい商品のトレンドを収集に行かなければならないと考え始めていた。そんな折も折、井上優とモロゾフの松宮隆男のコンビが近畿ツーリストと組んだ、「ヨーロッパのマイスターを訪ねる旅行」が企画された。主として経営者のための企画であった。往復ともビジネスクラス、ホテルは超一流で費用も破格のもであった。私はオリムピア製菓の役員として参加した。妻の代わりに母親、オリムピア製菓の取締役副社長を帯同することになった。
旅程は1987年5月23日から6月1日までの10日間であった。参加者は下記の通り。
株式会社中央軒本店 社長 竹馬一雄、竹馬尚代
オリムピア製菓株式会社 副社長 富永正枝、取締役 富永 勸
株式会社お菓子の紅香梅 社長 副島 隆
株式会社タカキベーカリー 課長 矢野完爾
株式会社近鉄百貨店 部長 沢田 孝
株式会社藤本達也事務所 社長 藤本達也
青木美代子
井上 優、井上洋子
近畿日本ツーリスト株式会社
渋谷海外旅行支店 支店長 田茂重穂
以上、12名。
井上優を語るとき私は常にモロゾフとの関連で前後のことが脳裏に浮かんでくる。松宮隆男が井上優を深く慕って、ライフスタイルマーチャンダイジングに傾倒していった。「バレンタインセール」をモロゾフだけが違うアプローチを試みていた。バレンタインをチョコレートの祭りととらえ、祭りには神様がいるという発想でテルニのバレンチノ教会に通っていた。これも井上優のマーチャンダイジングから生まれたものであった。テルニに通い始めて、「中世、愛の小径」のキーワードが生まれ、1978年1月には「スイートランド」に<中世・愛の小径>特集号が発刊された。この頃、井上優は「マイスター、(匠)」に凝っていた。この旅行のテーマがマイスターであることからも分かる。私も井上優に強く影響されイタリアに住居を購入するところまでのぼせ上がったのであった。
<つづく>

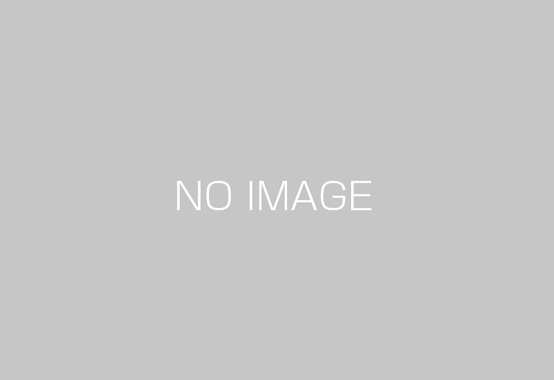



この記事へのコメントはありません。